化学メーカーに就職することになって「高分子化学」を勉強しなくちゃいけなくなったけど、最初の1冊には何が良いの?
化学メーカーの営業職に就職が決まった。細かい内容は置いておいて、最低限の「高分子化学の内容」を概要を抑えておきたい!
化学メーカーの多くは高分子材料をメインに扱っています。学生時代に低分子合成を専攻していた人や文文系出身の人にとっては、「高分子化学」は取っ付きにくい分野です。しかし、化学メーカーに勤務すると、「高分子化学」に触れる機会が必ず出でてきます。
これまで「高分子化学」に触れてこなかったけど、化学メーカーに就職し「高分子化学」を学ぶ必要がある人には、まず下記の「高分子化学の基本と仕組み」をおすすめします。
この記事では「高分子化学の基本と仕組み」の概要・到達レベル・使い方を紹介します。
「高分子化学の基本と仕組み」の概要
「高分子化学の基本と仕組み」の概要は下記です。
- 高分子化学の基礎・教養レベルの事項を網羅
- 図解・シンプルな解説でわかりやすい
- 高分子化学の教養レベルの内容は習得できる
難易度・網羅性などのスペックは下表の通りです。
| 難易度 | 入門・教養レベル 最も簡単なレベル |
| 解説 | 図解が多い、わかりやすい |
| 網羅性 | ★★★★☆ 基礎事項は網羅している |
| 独学しやすさ | ★★★★☆ |
| おすすめ度 | ★★★★★ 初学者には最もおすすめ |
「高分子化学の基本と仕組み」は、高分子の「教養レベルの基礎事項」を網羅的に学ぶための本です。高分子化学の基礎事項が図解を用いて、わかりやすく解説されており、短時間で高分子の基礎を抑えることができます。
本書を勉強しておけば、高難度の教科書を学ぶための基礎が身につきます。
化学メーカーに勤務するけど「高分子化学」を学んだことがないという人には、最初に読んで欲しい一冊です。
「高分子化学の基本と仕組み」の難易度
「高分子化学の基本と仕組み」の難易度は下記のようになります。
- 高分子科学の超基礎レベル(教養レベル)
「高分子化学の基本と仕組み」は基礎事項に絞って解説された本です。
難易度としては「超基礎レベル」です。本書を読み終えれば教養レベルの高分子化学の知識は網羅できます。「高分子化学」の基礎を網羅的・短時間でおさえることが可能なため、最初の一冊におすすめです。
「高分子化学の基本と仕組み」の対象者
- 化学メーカーに就職して、はじめて高分子科学を学ぶ人
- 最低限の知識さあれば良い人
化学メーカーに就職して、はじめて高分子科学を学ぶ人
「高分子化学」以外を専攻していた人に本書はとてもおすすめです。「高分子化学」では「合成」の内容や、数式が頻発する「物性」の内容など、学ぶべき内容が多岐に渡ります。本書では、それぞれの内容を網羅的にシンプルに解説してくれます。そのため、はじめて「高分子化学」を学ぶ人が概略と重要用語を短時間で抑えるためにとてもおすすめです。
最低限の知識さあれば良い人
文系出身者のような「最低限の知識があれば良い!」という人には「高分子化学の基本と仕組み」が最もおすすめです。営業職などの人は「最低限の知識」さえあれば、顧客とのやり取りにも困ることがなくなり業務を遂行できるようになると思います。
「高分子化学の基本と仕組み」のメリット
- 図解が多く、わかりやすい解説
- 教養レベルの内容は網羅
- 短時間でが読める
図解が多く、わかりやすい解説
「高分子化学の基本と仕組み」では、図解を用いて端的にわかりやすく解説してくれます。そのため、初学者でも躓くことなく、読み進めることができます。
初めて「高分子化学」を学ぶ人にはとてもおすすめです。
教養レベルの内容は網羅
「高分子化学の基本と仕組み」は、「高分子化学」を学ぶなら確実に知っておく必要がある基礎・教養レベルの事項をすべて網羅しています。
「最低限の知識を勉強できれば十分!」という人には、本書でサクッと教養レベルの事項を勉強してしまうのがおすすめです。
短時間でが読める
「高分子化学の基本と仕組み」は説明がシンプルでわかりやすく、教養レベルの事項にのみ絞って解説されていることもあり、短時間で読み終えることができます。
「できるだけ短時間で概要を抑えたい・教養レベルで十分」という人には、最適な1冊です。
「高分子化学の基本と仕組み」のデメリット
- あくまで教養レベル
- 問題演習がない
あくまで教養レベル
「高分子化学の基本と仕組み」をマスターしても、身につくものは「教養レベル」の知識です。この本だけで研究・開発を行えるレベルには到達できません。
ただし、本書を読めば、高度な内容を理解するための知識が得られます。今後、より難しい内容まで学んでいく人でも、まずは本書から勉強することをおすすめします。
問題演習がない
「高分子化学」の知識を身に付けるには「教科書で知識をインプット」→「問題演習を通してアウトプット」の流れが重要です。しかし「高分子化学の基本と仕組み」には演習問題が付いていません。
簡単なものでも良いので、問題の章も付属してほしかったところです。
「高分子化学の基本と仕組み」の使い方
「高分子化学の基本と仕組み」のおすすめの使い方は次のようになります。
- はじめの章をざっと読む
- その章を読み終わったら、もう一度その章を精読する
- 同様の手順で次の章に進む
- 最後の章まで進めたら、最初から周回する
はじめの章をざっと読む
まずは、最初の章をざっと読んでいき、大まかな内容・流れを掴みましょう。「高分子化学の基本と仕組み」では、図解が多く用いられています。この図解がとてもわかりやすく「高分子化学」をイメージしながら理解できるようになっているので、しっかり見るようにしましょう。
その章を読み終わったら、もう一度その章を精読する
ざっと読み終わったら、再度その章を精読していきましょう。特に用語などは、しっかりイメージ・意味を確認しながら、読んできましょう。
完璧でなくてよいので、ざっくり用語を覚えるつもりで読み進められると尚良いです。
同様の手順で次の章に進む
次の章でも同様の方法で進めて下さい。
最後の章まで進めたら、最初から周回する
最後の章まで終わったら、最初から周回しましょう。1周で全てを理解できる人はいないので、必ず周回をするようにしましょう。
「周回」は地味でめんどくさい作業ですが、「周回」によって知識が定着します。2周目以降は、1周目の半分以下の時間・労力で進めていくことができるので、めんどくさがらず、最低でも3周は周回してください。
「高分子化学の基本と仕組み」の到達レベル
「高分子化学の基本と仕組み」の到達レベルは下記のようになります。
- 教養レベルの事項は網羅
- 高分子を学ぶための準備が完了
教養レベルの事項は網羅
「高分子化学の基本と仕組み」をマスターすれば、最低限の知識は網羅できます。
文系職の方は、この知識だけで十分だと思います。後は業務の中で担当する製品の知識を深めていけば良いと思います。
高分子を学ぶための準備が完了
「高分子化学の基本と仕組み」は基本を解説した本ですが、しっかり身に付けられれば、より高難度の専門書も読み進められるだけの力が身に付きます。
研究開発職の人は、より高難度の専門書で勉強する必要がありますが、「高分子化学の基本と仕組み」を勉強しておけば、そういった高難度の内容も理解できる基礎力が身につきます。
「高分子化学の基本と仕組み」の次
「高分子化学の基本と仕組み」の次は以下の教科書がおすすめです。
この「高分子科学 合成から物性まで」は「高分子化学の基本と仕組み」より専門的な書籍になります。
この「高分子科学 合成から物性まで」を勉強しておけば、メーカーの研究開発職としてギリギリやっていけるレベルに到達できます。研究開発職の人は「高分子科学 合成から物性まで」をマスターすることを目標にしましょう。
「高分子科学 合成から物性まで」の詳細は下記記事で紹介しているので、是非ご覧ください。
「高分子化学の基本と仕組み」のまとめ
今回は「高分子化学の基本と仕組み」を紹介しました。「高分子化学の基本と仕組み」の特徴は下記です。
- 高分子化学の基礎・教養レベルの事項を網羅
- 図解・シンプルな解説でわかりやすい
- 高分子化学の教養レベルの内容は習得できる
「高分子化学の基本と仕組み」は、高分子化学初心者が「高分子化学とはどういった学問か?」を抑えるのに最適な教科書です。ただし、学べるのは「教養レベル」です。研究・開発職レベルには足りません。一方、文系職の人には十分すぎる内容です。
いずれにせよ「高分子について全くわからない」という初心者は、入門書として「高分子化学の基本と仕組み」から勉強を始めてみることをおすすめします。
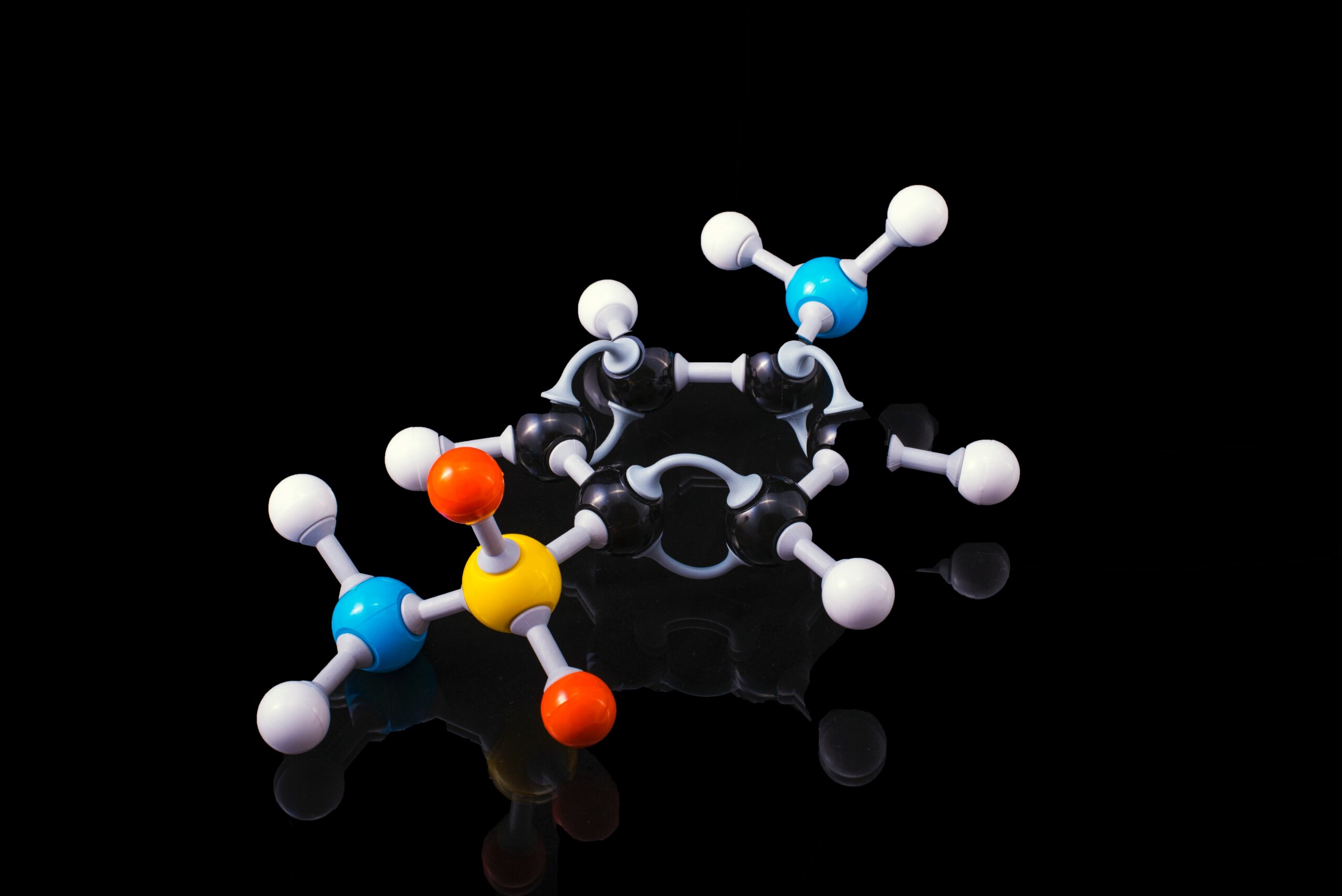







コメント