医薬品って体の中でどんな風に作用しているの?
医薬品はどういう風に研究開発されているの?医薬品メーカーの研究職に就くには何を勉強すれば良いの?
医薬品メーカーに興味のある人の中には、このように考えている人も多いはず。そのような人には「医薬品の化学」を読むことをおすすめします。
この記事では「医薬品の化学」の概要を紹介します。
「医薬品の化学」の概要
「医薬品の化学」の要点を述べると下記のようになります。
- 有機化学を専攻している人が「医薬品化学」を始めて学ぶのに最適な本
- 「医薬品」が体の中でどのように作用して病気が治癒するのか解説してくれる本
- 「医薬品」がどのように開発されているか解説してくれる本
「医薬品の化学」は、有機化学の視点から「医薬品」の基礎をわかりやすく解説してくれる本で、「医薬品化学」をはじめて学ぶ人に最もおすすめできる本です。本書を読めば、「医薬品」が病気を治すメカニズムと「医薬品」がどのように開発されているかが理解できます。
医薬品の作用メカニズムは、有機化学で学ぶ反応機構に共通する部分が多く、有機化学を学んだことがある人なら「体内で起こる有機反応」と「その有機反応のおかげで病気が治癒する」という事実に感銘を受けると思います。それと同時に「医薬品の開発」の難しさも理解できると思います。
「創薬」に携わりたい人は、本書を読んでおくことで、日頃から、どの様なことに着目して勉強しておけば良いかが解るようになります。
「医薬品の化学」がおすすめの人
- 有機化学を学んでいて、将来「医薬品開発」に携わりたい人
- 医薬品開発に携わることになった初学者(時間がない人)
- 医薬品がどのようにメカニズムで病気を治すのか理解したい人
有機化学を学んでいて、将来「医薬品開発」に携わりたい人
有機化学を専攻する人の中には、「将来は製薬メーカで、創薬の仕事に携わりたい」という人が多いと思います。そのような人の中には「創薬メーカーでの仕事内容・流れ」を把握できていない人もいると思います。
本書を読めば「薬の作用メカニズム」と「医薬品開発とはどういたものか?」が理解できるため、事前に本書を読んで「医薬品開発」とはどういったものかを把握し「本当にやりたい仕事なのか」考えることをおすすめします。
医薬品開発に携わることになった初学者(時間がない人)
既に製薬メーカーに就職が決まった人・急に医薬品開発に携わることになって人にも「医薬品の化学」は大変おすすめです。
上記のような人の中には、時間がない人も多いと思います。本書は大変読みやすく、「医薬品」について基礎から最短で学習できる教科書なので、時間がない人にもおすすめできる本です。
医薬品がどのようにメカニズムで病気を治すのか理解したい人
「医薬品の化学」では、薬が病気を治癒するメカニズムを解説してくれます。例えば、「医薬品のこの官能基が、受容体のこの部分と反応し、病気を治癒する」といった様に、有機化学の反応機構を用いて解説してくれます。
薬の作用機構を知りたい人は、本書を読めば、薬が体の中でどのように振舞っているのか理解できるようになります。
「医薬品の化学」の良い点
- 「医薬品」が病気を治すメカニズムを有機化学的な観点から解説されている
- 「医薬品」がどのように開発されているか解説してくれる本
- 「医薬品」を理解するのに必須な有機化学の基礎事項から解説してくれる
「医薬品」が病気を治すメカニズムを有機化学的な観点から解説されている
前述のように「医薬品の化学」では、薬が病気を治癒するメカニズムを解説してくれます。「医薬品分子中の官能基が受容体中のこの部分の官能基と反応して、ウィルスの増殖を阻害する」といった形で、有機化学を専攻している人なら簡単に理解できるように解説してくれます。
医薬品のメカニズムを理解できれば応用の効く知識が身に付くので、医薬品を開発する立場になっても役立ちます。
「医薬品」がどのように開発されているか解説してくれる本
「医薬品の化学」では、医薬品がどのように開発されているのか把握できます。本書を読めば、医薬品「医薬品開発」の地道さ・難しさ・課題がわかります。
医薬品開発を目指す人は、本書を読んで、その難しさに触れておき、日頃からどのようなことに着目して、勉強しておくべきか考えられるようになります。
「医薬品」を理解するのに必須な有機化学の基礎事項も解説してくれる
「医薬品の化学」を理解するためには、有機化学の知識が必須となります。本書では、最初の章で、「医薬品ための有機化学の基礎」を解説してくれます。
そのため、有機化学を忘れかけている人でも本書を読い進められる構成になっています。
「医薬品の化学」の悪い点
- 「有機化学」の知識がないと読み進めづらい
- かわいい表紙だけど高度な内容も含まれている
- 体系的にまとめられていない
- 網羅性が高くない
「有機化学」の知識がないと読み進めづらい
「医薬品の化学」では、有機化学の基礎から解説してくれていますが、それでも事前に有機化学の知識を身に付けた後の方が読みやすいのは事実です。
医薬品の合成スキームが掲示される箇所もあるのですが、そういった部分はある程度の有機化学の知識がないと理解するのが難しいです。
そのため、まずは有機化学の知識を身に付けてから。本書を読み始めることをおすすめします。下記の記事「有機化学のおすすめ教科書」で紹介している教科書の中から、最低でも「初級レベル」の教科書を、できれば「中級レベル」の教科書を勉強しておきましょう。
かわいい表紙だけど高度な内容も含まれている
「医薬品の化学」の表紙は非常に可愛いです。可愛い表紙なので簡単な内容かと思われますが、割と高度な内容まで含まれます。
というのも「医薬品化学」の分野自体が応用的な学問領域なため、基礎レベルの本でも一定以上のレベルになってしまいます。
表紙の可愛さに騙されないように注意が必要です。
体系的にまとめられていない
「医薬品の化学」では、多くの医薬品の構造や治癒メカニズムが紹介されていますが、重要なトピックのみを紹介した内容であり、体系立って説明されているわけではあります。
そのため、より体系的に学びたい人は、本書の後に、他の教科書で勉強することをおすすめします。ただし、本書は他の教科書よりわかりやすく、医薬品化学の概要を掴むのに最適な教科書なので、まずこの「医薬品の化学」を読み、「医薬化学」の概要を抑えた後に、より体系的に学べる教科書で勉強するルートををおすすめします。
網羅性が高いくない
前述の通り、「医薬品」の分野は応用的な学問領域であって、その領域は極めて広いです。1冊の本で全ての医薬品を解説するのは到底不可能です。本書においても、紹介されている医薬品は一部のものだけで、網羅性はそこまで高くはありません。
ただし、この本を理解しておけば、他のより高度な本を読むための基礎知識は十分身に付くので、まずは本書から勉強してみることをおすすめします。
「医薬品の化学」の学習手順
- 事前準備:「有機化学」の基礎知識を学ぶ
- わからない部分は有機化学の教科書で調べながら、読み進める
- 気に入った部分や感銘を受けた部分はマーキングやメモしながら読む
- もう1周
事前準備:「有機化学」の基礎知識を学ぶ
「医薬品の化学」を読み始める前に、「有機化学」の基礎事項を学習しておいた方が良いです。
下記の記事「有機化学のおすすめ教科書」で紹介している教科書の中から、最低でも「初級レベル」の教科書を、できれば「中級レベル」の教科書を勉強しておきましょう。
わからない部分は有機化学の教科書で調べながら、読み進める
有機化学の基礎事項を身に付けたら、本書を読み進めましょう。本書の第一部は有機化学の基礎事項の解説になりますが、復習がてら読みましょう。忘れている部分やあいまいな部分があれば、この機会に調べなおすなどして知識を補完するようにしましょう。
読み進める中で、理解できない部分があれば、有機化学の教科書で調べながら読んでいきましょう。
気に入った部分や感銘を受けた部分はマーキングやメモしながら読む
本書を読み進める中で、「薬の作用メカニズム」などの気に入った部分などがあれば、マーキングやメモをしながら読んでいきましょう。このマーキング・メモの部分は後から復習する際にとても役立ちます。
もう1周
最後まで読み終えたら、もう1周読みましょう。
2周目では、1周目でマーキングやメモした個所を中心に読み進めていきましょう。マーキングやメモ部分を活用しながら読み進めることで、短時間で効率的に2周目を完了できます。
「医薬品の化学」の到達レベル
- 「医薬品」の開発され、有機化学がどのように利用されているのかざっくり理解できる
- 「医薬品」が病気を治すメカニズムがざっくり理解できる
「医薬品の化学」を読めば、上記の2つをざっくり理解できているレベルの到達できます。あくまで「医薬化学」の概要をつかめただけです。
前述の通り「医薬化学」は、応用的な分野で、範囲も広いので、本書だけで勉強を完結できることはありません。
医薬品業界で仕事をするなら継続的な勉強が不可欠であって、より網羅的・体系的に「医薬化学」を学ぶ必要があります。
「医薬品の化学」の次
「医薬品の化学」の次の教科書としては以下をおすすめします。
この教科書では、「医薬品化学」「創薬化学」について体系的・網羅的に解説されています。加えて、実際の医薬品の開発現場での、実験の流れや権利化などについても振れられています。
内容は高度ですが、この1冊で多くのことが学べるので「医薬品の化学」の次の教科書として大変おすすめです。
「医薬品の化学」のまとめ
「医薬品の化学」は、医薬化学・創薬化学の入門に最適な教科書です。「医薬品の化学」の要点は下記。
- 有機化学を専攻している人が「医薬品化学」を始めて学ぶのに最適な本
- 「医薬品」が体の中でどのように作用して病気が治癒するのか解説してくれる本
- 「医薬品」がどのように開発されているか解説してくれる本
医薬化学・創薬化学をはじめて学ぶ人、医薬化学・創薬化学を短時間で学ぶ必要がある人は、まず本書から読んでみましょう。
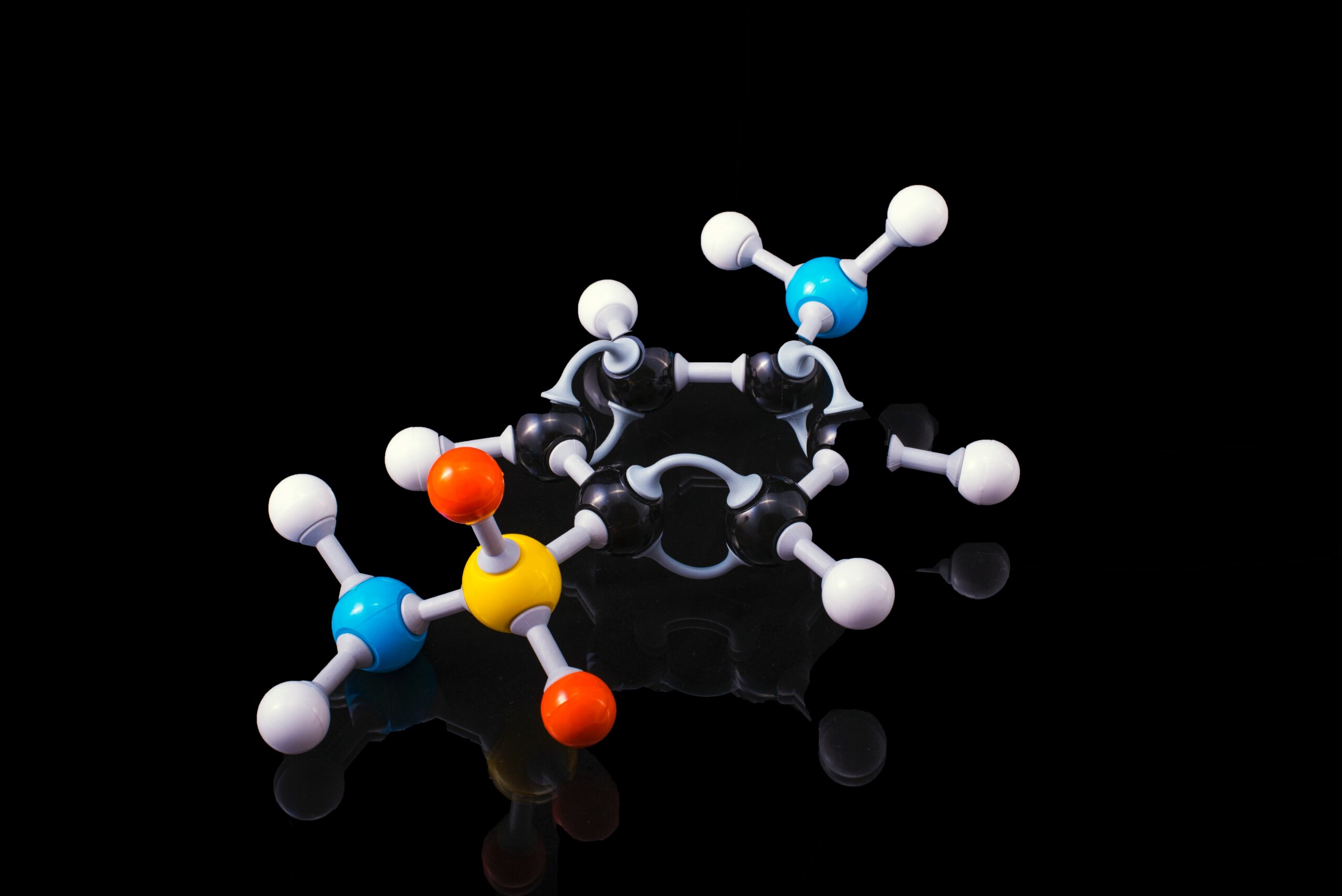




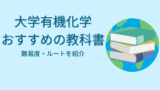


コメント